『俺たちの旅』『傷だらけの天使』など、昭和の名作テレビドラマの最終回を、『週刊現代』(2015年1月17・24日号)が特集しています。カラーページでは、『あの「TVドラマ」最終回はこうでした』という特集ページを、前半と後半に分けて8ページずつ掲載しています。
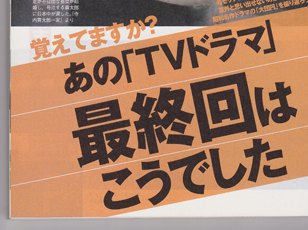 『週刊現代』(2015年1月17・24日号)より
『週刊現代』(2015年1月17・24日号)より
どちらも、昭和の人気ドラマの最終回を振り返るものです。
前半は、8ページのうち7ページが、『いま見てもグッとくる名作ドラマの「ラストシーン」』と題して、テレビドラマ史で真っ先に取り沙汰されるドラマについて、主演俳優の談話も入れながら最終回を解説しています。
登場する作品は、『寺内貫太郎一家』『
われら青春!』『おしん』『
金曜日の妻たちへ』『
岸辺のアルバム』『北の国から』『3年B組金八先生』など。
 『TV青春白書』(東京ニュース通信社)より
『TV青春白書』(東京ニュース通信社)より
そして、最後の1ページで、岡田晋吉(元日本テレビプロデューサー)、柏原寛司(脚本家)という、とくに70~80年代のテレビドラマ史を語る上で重要なクリエーター2人が、『「史上最強の最終回」はこれだ!』というタイトルで、当時のドラマづくりについて振り返る対談を行っています。
 『週刊現代』(2015年1月17・24日号)より
『週刊現代』(2015年1月17・24日号)より
後半の8ページは、『ジャンル別感動場面をもう一度』という見出しで、文字通り「好視聴率だった最終回」「大河ドラマ」「青春ドラマ」「ホームドラマ」「刑事・探偵ドラマ」と、ジャンルごとに当時人気ドラマだった各作品の最終回を振り返っています。
このブログで以前記事にした、『
積木くずし』『
男女7人秋物語』『
ゆうひが丘の総理大臣』『
おれは男だ!』『
パパと呼ばないで』などは入っています。

ただ、「ホームドラマ」といいますが、『肝っ玉かあさん』や『ありがとう』など、石井ふく子プロデューサーの手がけたお化け番組は一切出てきません。
それらはDVD化されていないので、記事はDVDのペイドパブ(ステマ)なのかもしれません。
何しろ、他のドラマの記事は、写真の片隅にDVDが発売されていることをさり気なく記していますから。
また、刑事ドラマには渡哲也の作品が、『大都会 闘いの日々』『
西部警察』と3作中2作、しかも残りの1作は前半の『太陽にほえろ』ですでに登場している松田優作の『探偵物語』です。
刑事ドラマは数えきれないほど作られているのに、ジャンル名に「探偵」とわざわざ加えたのは、とにかく松田優作を入れたかっただけではないかという、かなり偏った選び方であることは否めません。

そういう問題点(笑)を差し引いても、当時の作品を見ていた人にとっては、懐かしく思える読み物だと思います。
スポンサードリンク↓
作品が視聴者や関係者と馴染んだから“名作”になった
前半の岡田晋吉×柏原寛司対談に話を戻します。
岡田晋吉プロデューサーは、「史上最高の最終回」として『俺たちの旅』を選んでいます。

「放映当初は最終回の内容を設定しないで撮り始めた。カースケとオメダが洋子を取り合うなかでラストは決めよう、ってね。でもだんだん心情的にどちらかとっていうのが辛くなった。それで、どっちともくっつかずに3人が別れてるんです」と語っています。
放送当時は、「オメダと洋子を一緒にしてくれ」という投書が多くて迷ったそうです。
もしそうなったら、ちょっと暗いカップルになったでしょうね。
柏原寛司氏は、『傷だらけの天使』を挙げています。
最終回は、木暮修(こぐれおさむ、萩原健一)が、肺炎で死んでしまった相棒の乾亨(いぬいあきら、水谷豊)を、ドラム缶に入れて夢の島に捨てて逃げてしまうという救いのないエンディングでした。
岡田晋吉プロデューサーによると、「ショーケンと、市川森一(脚本)と清水欣也(監督)が話し合ってああなった」と振り返っています。
それを受けて柏原寛司氏は、「主役の木暮修と乾亨のキャラクターが第1話と最終回では違っている。でもコンビネーションは明らかに良くなっていて、視聴者もストーリーに入り込めるようになっていった。それは『俺たちの旅』の3人にも言えますね」と結んでいます。
ここで私が思ったこと。
やはり今のドラマが、昭和の作品ほど感情移入できないのは、今の作品は1クール(3ヵ月)、回数にすると10回か11回で終わってしまうからではないか。
昭和のドラマは、多くが2クール。視聴率が良ければさらに延長しました。
最初はなじめない駄作でも、作品との“長い付き合い”の中から視聴者もこだわりができるようになり、役者やスタッフも気持ちが入る。そうした思いが作品に反映され、ストーリーやキャラクターに変更が加えられることもある。
それによって、当時は高い視聴率ではなかった作品でも、それなりに思い入れが蘇ってくるのではないでしょうか。
どんなに面白いストーリーや役者の熱演で作られても、3ヶ月でバタバタっと終わってしまったら、気持ちの入れようがないですよね。心には残りません。
『家政婦のミタ』(2011年10月12日~12月21日、日本テレビ)のように、平成に入ってから記録的な視聴率を叩きだした番組もあるのですが、視聴者の記憶に残るためには、数字だけではないのです。
今は視聴率も、番組途中の瞬間視聴率なるものまでみる数字第一主義の時代です。
そして短期集中で切り上げ、その勢いでスポンサー料の高いスペシャル番組や映画化やDVD化という二次利用の戦略をとっています。
が、あえて逆張りで、昔のように、作品が視聴者や役者・スタッフに“馴染む”まで辛抱できるスポンサーが出てこないものかな、なんて思います。
いつも書いていますが、株で言うキャピタルゲインではなく、
インカムゲインを狙う作品です。
お金を出す企業としてのメリットはわかりませんが、少なくとも作品の価値づくりは長い目で見るとその方がいいんじゃないかなという気がします。
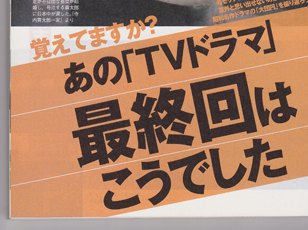





Facebook コメント