
Amazonが、これまで新品である限り同一価格で販売されていた書籍について、値下げ販売を検討すると発表しました。それによって、とくに中小書店、零細出版社、作家などに影響が心配されます。“書籍販売の新自由主義”は波紋を呼びそうです。
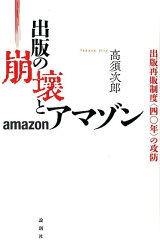
書店で売っている書籍は、委託販売と言って、売れなければ出版社に返品します。
価格を下げて、叩き売りしてはいけないのです。
これを、著作物の再販制度(再販売価格維持制度)といいます。
ところが、Amazonが、売れ残っても出版社に返品しない「買い切り」にするかわりに、売れ残った場合は出版社と協議して値下げも検討すると発表したのです。
市場経済を標榜する我が国では、商品の価格は市場原理で決まることになっています。
売れなければ価格は下がり、価値が高くなれば価格も高くなります。
ところが、日本では表現媒体である新聞、書籍、雑誌、音楽CDの4品目は再販価格維持の対象として、メーカーが定めた価格を変えてはならないことになっています。
今回のAmazonの発表は、収益を圧迫する高い返品率の引き下げにつながるとの期待の一方で、中小書店への影響を懸念する声も出ています。
Amazonが本の安売りを始めたら、ただでさえ書店数が減っているときに、いよいよ壊滅的な打撃を受けるだろうということです。
ネットの議論を見ていると、誰のためになり、誰のためにならないかということの判定がなかなかむずかしいようですね。
⇒
Amazonが書籍「買い切り」書店が本を値下げへ
再販売価格維持制度をぶっ壊せという人たちは、この制度によって新聞社が莫大な利益を得ているからけしからんといいます。
それはたしかにあります。
ただし、この制度による利益を享受すべき切実な対象は、新聞社ではなく零細の出版社や作家なんです。
ですから、新聞社が儲かっているからという理由だけで、制度全体をなくせという「既得権益反対」の論理には、私は賛成できません。
昨今は、Kindleなど電子書籍の発行が始まり、それは紙代も取次店のマージンもかからないから、零細出版社は電子書籍に特化すればいい、という意見もあります。
しかし、老若男女すべての人が電子書籍で読めるわけではありませんし、コピーが可能な電子書籍の場合、思ったほどの売上げを出せるかどうかは甚だ疑問です。
また、電子書籍は僅かなページを公開する「立ち読み」なるサービスはあるものの、紙媒体のようにどこのページだろうが自由に立ち読みできる方が、実は売上が上がるという意見もあります。
音楽CDの価格自由化は、ただでさえAKB商法が問題視されているときに、いったいどうなってしまうんだろうという心配もあります。
スポンサーリンク↓
作家と出版社との契約はどういうものか
作家は、通常10%を印税としてもらう出版契約をかわしたとすると、たとえば価格1000円で初版5000部刷った場合、その5000部の売行きに関係なく50万が支払われます。
そして5000部捌けると増刷されますが、あとは売れた部数に応じて支払われます。
作家は、「50万」という固定された数字があるから、原稿を書いたり、取材をしたりできるのです。
しかし、このビジネスモデルは今回のAmazonの「価格破壊」によって崩れるのではないか、という懸念があるわけです。
数字が読めない書き物では仕事として成立せず、質も低下し、書き手も減ってしまうのではないか、それは文化的な損失ではないか、という話です。
書籍の市場価値は、作家の労力や文化的価値と必ずしもイコールではないので、それを市場価値に揃えられてしまうと、「売れないけど文化的には書いておきたい」という良書が出にくくなることは間違いありません。
世に発表ということにこだわるのだったら、作家が個人的に、食うや食わずを覚悟して、ブログや電子書籍で発表するというやり方もありますが、「食うや食わず」といったって、全く生活費を稼げなければ続きませんから、やはり「たつきの道」として成立するだけの対価はいただかなければなりません。
今回のAamzonの発表は、著作権業界の黒船といわれていますが、「本が安くなるんならいいじゃないか」という刹那的な考えではなく、「鎖国」をやめることで何を失うのか、そうなったらどう対応するのかといった議論はきちんと行っていただきたいとおもいます。
 まちの本屋
まちの本屋

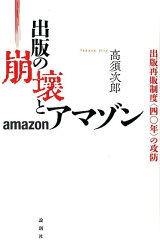

市場原理に、全てを委ねてしまうのは危険ですね。
「安いのがいい」→「儲かるのがいい」のような考え方が蔓延すると
いずれ産業ごとの就業バランスが、崩れるかもしれません。
by 犬眉母 (2019-02-16 02:04)
Amazonは“書籍販売の新自由主義”にいよいよ乗り出すか・・・こういう動きは本当に嫌ですね。いかにも書籍を「単なるコンテンツ」と捉えている感がありありで辟易させられます。文化芸術というものは人間の心に密着し、人間の心を救い、時に大きく向上させるものなのですが、新自由主義にはそうしたものに対するリスペクトはまったく感じられません。そりゃあ使い始めれば、使いこなせるでしょうが、「持っていて当然」という業界の傲慢な考えが気に入りません。キャッシュレス化なんかもそうですね。それとさらにいつも思っていることなのですが、わたしの母なんかスマホどころか、ガラケーのメールもできません。ご高齢の方々で、そういう人たち、多いと思います。しかし業界にとっては、そういう人たちは「いないも同然」で、新しいサービスが中心となって、ご高齢の方々にとっては逆に不便になることなんかお構いなしなのですよね。
>僅かなページを公開する「立ち読み」なるサービス
そうなのですか。使ってないので知りませんでしたが、立ち読みさえも業者の都合のままなのですね。もちろん電子書籍のすべてを否定する気はありませんが、紙の本の価値、街の本屋の意義など、大人たちがもっともっと発信していかねばと、つくづく感じます。
>AKB商法が問題視されているとき
結局、NGTの問題もうやむやになっていってますね。なにせメディアの扱いがあまりに少ないですから。この件についての情報をいろいろチェックしていると、最早「アイドル」という名もまったく程遠い、おぞましい実態が見えてきます。AKB商法はいずれ断罪されねばならないと強く思います。
>「売れないけど文化的には書いておきたい」
こういう本がなければ、わたし、読むものが無くなってしまいます。売上上位にランクインする本って、まず読まないです。今の日本の映画興行ランキングと同様に、ヒットしている作品にロクでもないのが多いです。もちろん例外もありますが(笑)。
ライブビューイングとクローズドサーキットはだいたい同じものだと思います。わたしもあまり詳しくはないのですが(笑)、クローズドサーキットというものは、アリVS猪木の時に知りました。当時はまだ、アリがどれだけとてつもないスーパースターであるかはもちろん、米国の地理もほとんど知らないボンクラなお子様だったのですが、「クローズドサーキット」という言葉だけで、(いったい何が始まるんだ!)と、ワクワク感が大きく増したことを記憶しております。
「日本映画界を代表する大女優、吉永小百合、天海祐希」と、確かに書かれてますね(笑)。
天海祐希はどのような意味でも「大女優」ではないですね。こうした文が生まれるのは、まず昨今の記者・ライターに「大女優」という概念を理解できている人が少なくなっているというのもあるでしょうし、「大女優吉永小百合と天海祐希」と書くと(笑)、天海祐希がもし読んだら気を悪くするかもとか考えたかもしれません。しかし天海祐希本人としても、対等のように吉永小百合と並べられては困ってしまうと思うのですが。特に女優の世界におれば、吉永小百合がいかに遠い存在であるか痛いほど分かるのではと思います。まあしかし、何はさて置いても、昨今のメディアの言葉づかいは腹立つものが極めて多いです。 RUKO
by 末尾ルコ(アルベール) (2019-02-16 03:23)
アマゾンがこの方針を実行できるとは自分には思えませんが、このニュースソースの信ぴょう性はいかがなものなのでしょうか。
現状これだけ売れるアマゾンに本を出さないという選択肢は出版社側にないと思いますので、どう対応するのか。もし本当に実行を断行しそうなら政府がアマゾンの規制に入るべきなのではと思うのですが。
by 足立sunny (2019-02-16 07:11)
安くなって活字離れが減り、紙の本が息を吹き返せばそれはそれで良い気がしますが、そんな事無さそうだしなぁ。
売れりゃ良い安けりゃ良いは結局身を滅ぼすだけだと思うんだけどなぁ。
by pn (2019-02-16 07:29)
書籍に限らず、自分の仕事もにたりよったりです。
携帯電話、通信関係の仕事をしてますが、価格競争が激しくてかなり賃金が安くなってます。
でも自分の使って携帯は、お世話になっているD社で使う側は料金が安いほうがたすかりますが。
by ヤマカゼ (2019-02-16 07:31)
街の本屋さんはますます苦境に落ち入りますね。
買い取りによって仕入れ価格も下がるでしょうが
消費者も通常価格では買わなくなるでしょう。
by kohtyan (2019-02-16 09:31)
ただ己の目先だけの考えでの止めるとか続けるとかではなくて、そうしたらどうなるということを100歩も200歩も先を読んで議論していただきたいです。
by なかちゃん (2019-02-16 15:10)
これから出版物や出版業界で生計を立てようと思う人にとっては切実な問題になりますね。
資本主義・市場経済の見直しが20世紀末から云われて未だ変化の兆しは無いけれど…あまり多方面で崩壊が起こるとタガが外れて一気に壊滅状態になる可能性もあります。その時一番被害を受けるのはやはり、従順な受け手である一般庶民なんでしょうね。
by 扶侶夢 (2019-02-16 17:24)
「安ければいい」というわけでもないですし、後になって自分たちの首を絞めることになるので、そこまで考えてほしいです。
by ナベちはる (2019-02-17 00:10)